
消化器内科

消化器内科
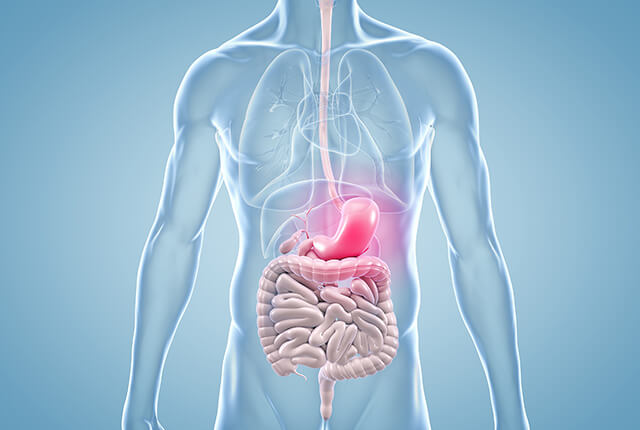
消化器内科は、食道・胃・十二指腸・大腸などの消化管および、肝臓や胆のう、膵臓などを幅広く専門的に診療します。消化器系の不調の症状としては、みぞおちの痛み(心窩部痛)、胃痛、腹痛、悪心(吐き気)・嘔吐、下痢、便秘、お腹の張り(膨満感)など様々なものがあります。
また、消化器系の疾患では重篤なものであっても、早期には自覚症状が現れることも少なくないため健康診断などで異常を指摘された場合は、できるだけお早めにご相談ください。
胃がんや大腸がん、その他の生活習慣病などのリスクが高まってくる40歳以上の方は、まず胃カメラ検査や大腸カメラ検査、エコー検査などを受けて、消化器系の健康状態を確認することをおすすめめします。当院では、胃カメラ・大腸カメラは日本消化器内視鏡学会専門医の院長が対応させていただきます。
食道、胃、十二指腸、大腸、肝臓、胆のう、膵臓などの病気に関して専門的な診療を行っております。
日常的に起こりやすい症状でも、詳細な検査を行うことで重大な病気の早期発見につながることもよくあります。
お腹の不調や気になることがございましたら、何でもお気軽にご相談ください。
胃液(胃酸)が胃の内容物とともに食道に逆流し、食道の粘膜に炎症が生じる病気です。胃酸が増えすぎてしまったり、胃酸の逆流を防ぐ機能がうまく働かなかったりすることで起こります。胃酸がのどまで上がってきて酸っぱいと感じるようになったり、胸やけやのどがヒリヒリしたりして不快感が続きます。喫煙、飲酒などの生活習慣や加齢、肥満、姿勢、食道裂孔ヘルニアなどが原因となります。
逆流性食道炎は、成人の10~20%がかかっていると推定されています。中高年、特に高齢者に多く見られます。薬物治療が基本ですが、同時に生活習慣の改善も大事です。
食道がんの主な原因は喫煙と飲酒です。特に日本人に多い扁平上皮がんは、喫煙と飲酒に強い関連性があるといわれています。また、喫煙と飲酒、両方の習慣がある人では、より危険性が高まるといわれています。食道がんは初期には自覚症状がほとんどなく、飲み込みにくいなどの症状があらわれるのは、がんがある程度大きくなってからです。がんが進行するにつれて、つかえ感、体重減少、胸や背中の痛み、咳、声のかすれなどの症状がでるようになります。早期に発見できれば内視鏡治療が可能です。飲酒や喫煙をされる方やバレット食道を指摘された方は、定期的に胃カメラ検査を受けることをおすすめめします。
急性胃炎は、胃の粘膜に炎症を起こす病気で、急激に発症します。激しい腹痛や胃の不快感、吐き気などの症状を生じ、重症の場合は吐血や血便がみられます。広範囲なびらんを伴う病変を、急性胃粘膜病変と呼び、アルコールの飲みすぎ、刺激の強い食べ物の摂取、ストレス、ピロリ菌感染、アレルギー、鎮痛薬・ステロイド・抗菌薬などの薬剤が原因と考えられています。
軽症の場合は薬物療法を行います。胃粘膜から出血していたり、自力での水分の摂取が困難な場合は入院治療が必要なこともあります。症状が強い、症状が長引く、何度も繰り返す場合は、胃カメラ検査をおすすめします。きちんと検査を受け適切な治療を受けましょう。
消化管の潰瘍は、炎症による傷が粘膜下層より深くまで至ったものをいいます。胃潰瘍とはこの病態が胃で、十二指腸潰瘍とは十二指腸で起こった疾患のことです。典型的な症状はみぞおちの鋭い痛みです。胸やけ、吐き気などを伴うこともあります。痛みは軽症の場合、胃潰瘍は食後に起こることが多く、十二指腸潰瘍は空腹時に起こることが多いというのが特徴です。進行すると常に痛むようになります。また、潰瘍が進行して血管を破ると出血し、吐血や黒または暗紫色のタール便が出る下血になることもあります。
ピロリ菌に感染することが主な原因として知られていますが、薬剤やストレスなどでも発症します。40代以降の方に多くみられますが、ピロリ菌に感染していると若い方でも発症することがあります。一般的には、胃・十二指腸潰瘍は胃酸を抑えるプロトンポンプ阻害薬(PPI)と粘膜を整える薬などの内服で比較的早く治すことができます。しかし、症状を我慢して、潰瘍が進むと、漿膜を突き破って穿孔を起こし、外科手術になってしまう可能性もあります。ピロリ菌が陽性の場合、ピロリ菌を除菌しなければ潰瘍の再発を繰り返し、胃がんも発症しやすくなりますので、必ず除菌をしましょう。
胃がんは胃粘膜から発生し、十数年かけて発見可能な大きさ(5㎜)以上になるといわれています。胃がんの原因はピロリ菌感染が多くを占めますが、喫煙や塩分の過剰摂取、栄養バランスの偏った食事なども要因と考えられています。胃がんは、世界の中で日本に多い病気です。かつては、日本人のがん死亡率第1位でしたが近年減少傾向にあります。しかし、胃がんの罹患数に関しては、高齢化の影響で非常に増えています。つまり、胃がんになる患者様は増加しているが、完治する人が多いため死亡数が変わっていないのです。この変化は胃がんの早期発見・早期治療の進歩が著しいからと考えられます。
胃がんは早期発見すれば、治る病気です。早期胃がんは、「初期であること」「サイズが小さいこと」などの条件さえクリアすれば手術で胃を切除することなく、内視鏡(胃カメラ)でがんの部位を切除すれば根治となります。胃がんは、ピロリ菌の除菌で予防を行い、胃カメラで早期発見をし、内視鏡治療で胃を切除せずにがんを根治を目指す時代です。
萎縮性胃炎は、胃の内壁にある粘膜が長期的な炎症により薄くなり、胃の機能が低下する疾患です。特に高齢者に多く見られる疾患ですが、ピロリ菌感染や食生活、ストレスなどの要因が関係しており、進行すると胃がんのリスクを高めることがあります。
ピロリ菌を除菌することでこの胃がんリスクを下げることが期待できますが、除菌後も未感染の方と比べ、がんの発生リスクが高いため、定期的な胃内視鏡検査が必要となります。
ヘリコバクターピロリ菌(H. pylori)は、胃の中に生息する細菌で、世界中で多くの人々が感染しています。この菌は、胃の中の強い酸性環境でも生き延びることができ、長期間にわたる感染が続くと胃の粘膜に炎症を引き起こし、胃潰瘍や胃がんのリスクを高めます。
ピロリ菌は、主に幼少期に感染することが多く、井戸水や食物を通じての感染、家族内で口から口への経路で感染するケースも報告されています。ピロリ菌は胃に定着し、適切な治療を行わない限り長期間にわたって感染が続くことが一般的です。内服薬で除菌をすることにより、胃潰瘍や十二指腸潰瘍を予防し、胃がんのリスクの低減が期待できます。ピロリ菌の除菌に成功した後も、定期的なフォローアップが重要です。特に萎縮性胃炎や胃がんのリスクが高い場合、定期的な内視鏡検査を受けることが推奨されます。
大腸がんは、大腸(結腸・直腸)に発生する悪性腫瘍で、腺腫という良性のポリープががん化したり、正常な粘膜から直接発生します。
平均寿命の高齢化に加え、食生活の欧米化など様々な要因もあり、大腸がんによる死亡者数は増加傾向にあります。大腸がんの発生率は40~50歳頃から急激に上昇します。大腸がんは早期の段階では自覚症状がほとんどなく、進行すると症状が出ることが多いです。初期の状態で発見・治療できれば、ほぼ100%治る可能性があります。大腸ポリープ切除術を行うことで、大腸がんによる死亡を予防できることも報告されています。
症状が出てから診断に至った場合には、内視鏡治療などの低侵襲な治療が選択できないこともあります。下痢や便秘などの排便異常、血便がみられる方や便潜血反応陽性の方は、早期の大腸内視鏡検査をおすすめめします。
便秘とは、排便が通常よりも困難または頻度が少なくなる状態を指します。便秘は誰にでも起こり得る一般的な消化器の問題ですが、その原因は多岐にわたり、放置すると慢性化し、生活の質を大きく低下させることもあります。便秘の原因は一つに限らず、生活習慣や体質、健康状態などさまざまな要因が関係しています。市販の便秘薬を利用する場合は、一時的な対処法として使用し、長期間の使用は避けるべきです。便秘薬の使用が必要な場合は、医師や薬剤師に相談することをおすすめします。
便秘は、多くの人が経験する一般的な症状ですが、放置すると生活の質を低下させるだけでなく、重篤な疾患の原因となることもあります。中には危険な便秘もあるので注意が必要です。強い腹痛や吐き気、発熱などを伴う場合や便に血が混ざる場合は自己療法で対処せずに、早めに医療機関での診察を受け、適切な治療を受けられることをおすすめめします。
感染性腸炎は、ウイルスや細菌、寄生虫などの病原体が腸に感染して引き起こされる炎症性疾患です。急性の腹痛や下痢、吐き気などを伴い、感染経路や原因となる病原体によって症状の重さや持続期間が異なります。感染性腸炎は、食べ物や水、接触などから感染するため、適切な予防と早期治療が重要です。感染性腸炎の治療は、主に症状の緩和と脱水症状の予防が目的となります。原因となる病原体によって治療法が異なりますが、まずは、水分補給。下痢や嘔吐によって失われた水分と電解質を補給することが最優先です。スポーツドリンクや経口補水液を使用し、脱水症状を予防します。特に幼児や高齢者は脱水のリスクが高いため、早めの対応が重要です。
次に食事。感染性腸炎の治療中は、消化に優しい食事(お粥やスープなど)を摂ることが推奨されます。高脂肪や辛い食べ物、カフェインを含む飲み物は避けましょう。
そして、内服治療。細菌性腸炎では適切な抗生物質が処方されることがあります。ウイルス性腸炎の場合は特定の治療薬がなく、対症療法が中心となります。
症状が軽度であっても、特に幼児や高齢者、免疫力が低下している人は早めに医師の診察を受けることが重要です。
日常的な衛生管理や食品の取り扱いに注意を払い、感染予防に努めることが、感染性腸炎を防ぐ最も効果的な方法です。
過敏性腸症候群(IBS)は、消化管に異常がないにもかかわらず、腹痛や下痢、便秘などの消化器症状が慢性的に続く疾患です。日本では多くの人が悩んでいる病気であり、特にストレスが引き金となることが多いといわれています。過敏性腸症候群の症状は、個人によって異なり、便秘型、下痢型、またはそれらが交互に現れる混合型があります。他の原因となる疾患がないことが診断上重要なので、血液検査、大腸カメラ検査を行います。
過敏性腸症候群は、生命に危険を及ぼす病気ではありませんが、症状が生活の質に大きく影響を与えることが少なくありません。日常生活や仕事、社会活動に支障をきたす場合もあり、患者様の精神的な負担が大きくなることもあります。適切な薬物治療と生活習慣の改善によって症状を管理することは可能です。特にストレス管理や食事の見直しが重要な役割を果たします。過敏性腸症候群で悩んでいる方は、一度消化器内科を受診し、適切な治療を受けることをおすすめめします。医師とともに長期的な治療計画を立て、ライフスタイルを見直すことが重要です。
潰瘍性大腸炎(Ulcerative Colitis, UC)は、大腸の粘膜に慢性的な炎症が起こり、潰瘍を形成する自己免疫性の疾患です。症状は悪化と緩解を繰り返し、長期にわたることが多いのが特徴です。難病に指定されており明確な原因は分かっていませんが、免疫機能の異常や環境要因が関与していると考えられています。
症状としては血便下痢、腹痛、重症化すると発熱、体重減少、貧血などがみられることもあります。
潰瘍性大腸炎は、血液・便検査、大腸カメラ検査で診断します。血液や便検査では細菌感染による大腸炎などの他の病気による炎症がないかを確認します。大腸カメラ検査は、大腸の粘膜に典型的な病変がないか、炎症や潰瘍の程度や範囲を確認します。
潰瘍性大腸炎の治療は、症状の緩解を目指すと同時に、再発を予防することを目的としています。薬物療法が一般的な治療法です。薬物療法で効果が見られない場合や、重度の合併症が生じた場合は、手術が選択されることがあります。手術では、大腸全体や一部を切除することが行われます。
潰瘍性大腸炎は、長期にわたって症状が続くため、生活の質に大きな影響を与えることがあります。適切な治療とライフスタイルの見直しにより、症状のコントロールが可能です。ストレス管理や食事の見直し、定期的な医師のフォローアップが重要です。
クローン病(Crohn’s Disease)は、消化管のどの部位にも炎症や潰瘍を引き起こす自己免疫疾患です。特に小腸と大腸に影響を与えることが多く、炎症によって腸の壁が厚くなり、潰瘍や狭窄が生じます。腹痛と下痢が高頻度にみられますが、発熱、栄養障害、血便、肛門病変(痔ろうなど)が現れることもあります。
内視鏡検査(大腸内視鏡・小腸内視鏡・カプセル内視鏡)では大腸や小腸の内側を直接観察し、炎症や潰瘍の有無を確認します。腹部のCTスキャンやMRIを用いて、腸の状態や合併症の有無を確認します。特に狭窄や膿瘍の有無を調べるのに役立ちます。
血液検査: 炎症マーカー(CRPなど)の測定や、貧血、栄養状態を確認するための血液検査が行われます。
クローン病の治療としては、内科治療(栄養療法や薬物療法)と外科治療があります。内科治療が主体となることが多いのですが、腸閉塞や穿孔、膿瘍などの合併症により外科治療が必要となります。
難病に指定されていますが、適切な治療で症状を抑制できれば健康な人と変わらない日常生活を送ることも可能です。消化に優しい食事を心がけ、栄養バランスを保つことが重要です。特に食物繊維の摂取量を調整し、適切な栄養を摂取することが推奨されます。ストレスが症状を悪化させる可能性があるため、リラクゼーションや趣味を持つことでストレスを軽減することが有効です。喫煙はクローン病を悪化させるため、禁煙が推奨されます。
何らかの原因によって肝細胞に炎症が起こり、肝細胞が壊されてしまう病態のことをいいます。肝機能障害が起きると肝細胞に含まれるALTやASTという酵素が血液中に漏れ出るため、血液検査の項目で異常として発見されます。原因には、ウイルス性肝炎(B型、C型肝炎が大半)、アルコール性肝障害、非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)、薬物性肝障害、自己免疫性肝炎があります。数値に異常があった場合は、生活習慣の改善に取り組み肝機能を高め、悪化を防ぐことが重要です。
胆のうの中に結石ができる病気です。胆石を持っている人の半数は無症状であるといわれています。無症状の場合には経過を観察することもあります。無症状の人に症状が出るのは5~10年で20~40%といわれています。症状としては、みぞおちを中心とした激しい痛みが典型的で、右肩や背中の痛みを伴う場合もあります。胆石症の症状は上部消化管の疾患による症状とよく似ているので、胃や十二指腸に病変がないことを、胃カメラで確認しておくことをおすすめします。
肝硬変は慢性肝疾患(B型肝炎やC型肝炎の肝炎ウイルス、脂肪肝、アルコール性肝障害など)において肝臓に線維組織が増加し、肝臓が硬くなる病気です。肝硬変の人の多くは、何年も無症状のままで、元気そうに見えます。その後食欲不振、体重減少、黄疸や腹水・浮腫といった症状が現れてきます。
膵液に含まれる消化酵素により、自らの膵臓を消化してしまう病態が急性膵炎です。原因として多いのは過度なアルコール摂取と胆石です。胆石が膵管の出口を塞ぐことにより膵臓に炎症が起こります。上腹部や背中の激しい痛みや嘔吐がみられ、黄疸や発熱を伴うこともあります。炎症が他臓器に広がりやすく、早期に入院治療が必要です。
膵臓がんは50~70歳、特に高齢の男性に多いがんです。
膵臓がんは特徴的な症状がなく、早期発見が難しいがんの一つです。初発症状は腹部違和感や食欲不振、体重減少といった他の疾患でも起こるような症状が多いといえます。病気が進むと、胃部不快感、腹痛、腰背部痛、黄疸などがみられます。現在、膵臓がんの原因ははっきりしていませんが、喫煙・膵嚢胞・糖尿病・慢性膵炎・膵臓がんの家族歴などが危険因子とされています。このような因子を持っている方は早期発見のため、積極的に血液検査や腹部超音波検査などを受けられることをおすすめめします。
